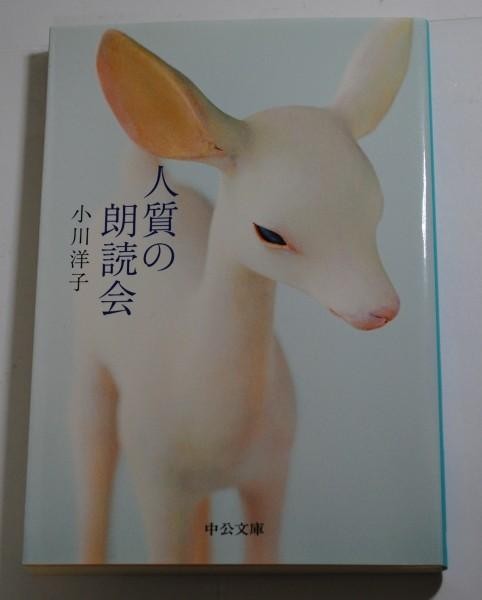連作短編集、ということになるのだろうか。その舞台としては、本のタイトルが示す通りとても特殊な設定がなされていて、冒頭で説明される。地球の裏側をゆく旅行会社のツアー参加者(日本人)が、現地の反政府ゲリラに襲われて拉致され人質となり、膠着状態の2か月ののち、犯人グループが仕掛けたダイナマイトにより全員死亡、という・・・。
本編となる8つの短編は、人質として過ごす日々の中で彼ら自身が語った過去の思い出話という趣向である。つまり、最初に衝撃的な事件と、その結末としての死がある。
読者も思わず緊張を強いられた格好で読み始めるが、そこで語られる物語のひとつひとつは、やはり小川洋子の筆致によるもので、とても静謐な雰囲気をたたえている。
静かなだけではない。風変わりで不可思議で、少し薄気味悪い。必ず、死や欠落がすぐそばにある。それでいて、紋切り型の展開や結末は決してない。悲しく、そしてあたたかい。
大して美味しくもなく、形だけは無数にあるというビスケット工場に勤め、がめつくて小うるさいアパートの大家と工場から持ち帰ったビスケットをシェアするのが日常になる主人公。たまたま両親がいないとき、隣に住むいわくありげな婦人に台所を貸すことになり、コンソメスープ作りを手伝うことになる主人公。何の変哲もない公民館で行われる数々の集いに足を踏み入れる主人公。なぜか様々な人に、「私の死んだおばあさんに似ている」と言われる主人公。
おしなべて突拍子のない物語だ。けれど小さなエピソードの隅々にまで精緻なディテールが張り巡らされているのでリアリティがすごい。ディテールは往々にして、妙なおかしみを醸しだしているのも特徴。こういうことって、あるよねと思う。取り立てて誰に語ったこともないけれど、自分の中に引っかかっているどこか不可思議なエピソードが、誰の人生にも。
最初の舞台設定―――衝撃的な事件と死―――があるので、それらの物語はとても深遠に響く。けれど本当は、これらすべては、彼らがどんなふうに生き、どんな終わりを迎えようと変わらない、過去の話だ。
映画にしろテレビ番組にしろ、往々にして、何かを成し遂げたという実績や、あるいは努力の過程を輝かしく評価することが多い気がする。実際、理不尽な事件や運命に遭って人間が亡くなったとき、メディアが報じる生前のエピソードもそれらの類だ。
本書は異なったアプローチをとっている。遠い場所で死に瀕している彼らが語るのは、実績でも努力でも、家族への愛情でもなく、いつかの、風変わりでおかしな出来事だ。わざわざ人に語って聞かせたことのないような。
けれどそのとき彼らの心が動いたこと、自分でもうまく消化できないような思いを抱いたことは事実で、そんな、言語化し難い事実や、思いが、生きているということなんだろうと思う。
とてもささやかだが、侵すことができない生の尊厳だと思う。
とてもささやかだが、侵すことができない生の尊厳だと思う。
彼らの話をテープに録って祖国にもたらしたのは、現地の特殊部隊のメンバーの一人という設定である。彼は、その任務の一環として監禁場所に盗聴器をしかけ、人質の朗読会をヘッドフォンで聞いていた。
その彼は、日本語がわからない、というのがミソだ。
彼は当然、話された内容をリアルタイムではひとつも理解できない。それでも、人質それぞれの声音や、日本語のリズムや、小さな咳払いや拍手を、小川のせせらぎのように好もしく聞いていた。
彼は当然、話された内容をリアルタイムではひとつも理解できない。それでも、人質それぞれの声音や、日本語のリズムや、小さな咳払いや拍手を、小川のせせらぎのように好もしく聞いていた。
最後に彼が語る逸話にもまた、「その意味はわからなかったけれど・・・」というエピソードが出てくる。突然訪ねてきた異邦人(日本人)とのコミュニケーション、けれど子どもだった彼が感じ取ったその優しさと確かさにすごく泣けた。無数の小さなアリが食べ物を運ぶ列、その虚しさを嘆くことなく過剰に讃えることもなく、「小川のせせらぎのよう」と彼は言う。敬服する思いで。
いくつか読んだ小川洋子の作品で、今のところこれが私のベスト。おすすめです。