『流』 東山彰良
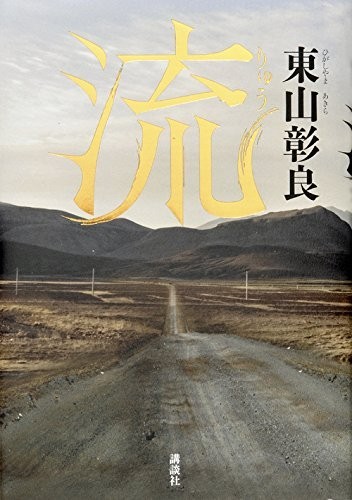
台湾出身の王貞月さんと知り合って話を聞いたのがきっかけで、『ゴロウ・デラックス』で著者・東山彰良さんがゲスト出演したのを見た。そこで紹介されていたのがこの本。読んでみた。
1975年、台湾。国民党総統・蒋介石が死んだのと同じ年に祖父が殺され、主人公・秋生の人生が大きく転回してゆく。
私は1978年生まれ、海外旅行で台湾に行ったことのある人も多い世代ではないかと思うが(私はない)、その近現代史については、私の世代以下ではあまり知らない人も多いんじゃなかろうか?
1911年、辛亥革命によって中華民国を建国した孫文の国民党を引き継いだのが蒋介石。国民党は、毛沢東が率いる中国共産党と対立関係にあり、日中戦争時こそ「国共合作」といって共同して日本に対抗したものの、戦後は中国国内で「国共内戦」に入る。敗北した国民党は中国を脱出、台北を中華民国の臨時首都とした。
このとき蒋介石と共に台湾へ渡ってきた中国人やその家族たちを「外省人」と言い、それ以前から台湾に住んでいた人々を「内省人」と言う。両者の住まう場所や階層がまだはっきりと分かれていた、物語が紡がれる1970年代は台湾にとってそんな時代だった。
主人公、秋生の祖父も、中国で抗日戦争を戦い、国共内戦後に妻子を連れて台湾へ逃れてきた一人だった。秋生は殺害の犯人を捜し始め、物語の中ではさまざまな形で日本の統治時代や国共内戦という激しい時代が回想されてゆく。
生前、祖父と公園で口論になっていたという岳さんは、日本統治時代を懐かしむ心を持っている。日本の同化政策によって、学校教育がすべて日本語で行われた時代に育った世代なのだ。岳さんはバイオリンで「朧月夜」を弾いている。そして言う。
「君のおじいさんはいつも不機嫌でした。胸のなかにまだ希望があったんでしょうね。
苛立ちや焦燥感は、希望の裏の顔ですから」
生前の祖父や、まだ生きている祖父の朋友たちは言う。
「わしらに大義なんぞありゃせんかった。こっちと喧嘩しとるからあっちに入る、こっちで飯を食わせてくれるからこっちに味方する。共産党も国民党もやるこたぁ一緒よ。他人の村に土足で踏みこんじゃあ、金と食い物を奪っていく
「戦争だったんだ。わしがおまえの家族を殺して、おまえがわしの家族を殺す。そんな時代だったんだ」
これらは、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』の一節を思い出させる。日中戦争の時代、中国での戦いについて語る浜野軍曹。
「私たちは匪族狩り、残兵狩りと称して多くの罪もない人々を殺し、食料を略奪します。戦線がどんどん前に進んでいくのに、補給が追い付かんから、私たちは略奪するしかないのです。(中略)少尉殿、この戦争には大義もなんにもありゃしませんぜ。こいつはただの殺し合いです。そして踏みつけられるのは、結局のところ貧しい農民たちです」
(『ねじまき鳥クロニクル』第1部)
若い秋生もまたやんちゃという言葉では表現しきれない、ハードな日々に足を突っ込む。暴力事件をきっかけに下位の荒れた高校へ転校せざるを得なくなったり、そこでさらに喧嘩の日々に明け暮れたり、ついにはやくざ者たちとの衝突がきっかけで軍隊に入ることになる。上官から拷問のような懲罰を受けたりもする。
秋生の日々における暴力的な側面はいかにも青春らしい刹那的な彩りのようで、その背後にある祖父たちの物語の大きさと激しさによって別の色合いが付加されるように思えた。やられたからやり返す・世話になった側について戦う・強い者が弱い者を虐げる・・・大義の無いそんな闘争が時代を超えて繰り返されている。人間の世界の愚かさとむなしさ。
一方で、豆花(台湾の伝統的スイーツ)や、釘でお尻を怪我する事件など、子ども時代の主人公と祖父との主では涙腺を刺激する甘やかな切なさにみちている。主人公が知る祖父の優しさ、偏屈さ、ユーモア、そして誰かの口から語られる、戦争の時代の祖父の鬼神のような強さや思いきりの良さ、敵に対する残酷さ・・・。
時代の風雲を潜り抜けてきた老人たちのあけすけさには大陸的な風を感じ、2つ年上のマオマオとの恋のくだりは'70年代の香り、そして続く夏美玲との関係では先進国になった日本が舞台で、つまり現代性を帯びてくる。
長いスパンを物語に組み込み、しかも意図的に交差させた描き方をすることで、固有の事件や歴史そのものも超えた、何か普遍的な、大きなものを感じさせる小説だった。というと、たいした手練れのようだけど、作風にはみずみずしい感触がある。
筆者は物語のラストに、命が息づく喜びの場面をもってくる。でも、その後年、何が起こってどうなるか、その暗転を、筆者は物語の半ばで既に示しているのである。私たちは固有の時代に生きて固有の経験をしながらも、どの時代でも似たような喜びや苦しみや愚かさを繰り返し、永遠に逃れられないメビウスの中にいるのだろうか? いや、そんな焦燥感は、自分が人生に、世の中に対して抱いている希望の裏の顔なんだろうか。人はどんな時代にもどんな苦しみの中にも、面白いこと喜ばしいこと甘やかなことを享受し、言葉にできない自分なりの真実をつかみとるものかもしれない。